野鳥の説明一覧
- [更新日:2022年10月28日]
- ID:91
コサギ

シラサギの代表ともいえるサギでもっともポピュラーな鳥の一つです。本州から九州で繁殖し、越冬するものが多くいます。
湿地、水田、河川、湖沼、干潟などで餌をとります。一年中黒いくちばしと黄色の足指をしていますので、ほかのサギ類と見分けられます。夏羽では後頭から2本の長い冠羽、背に先のカールした飾り羽が出ています。
中村川や葛川の水辺で、足指をふるわせて餌の小魚や水生昆虫を追い出すユニークな動作を行う姿を観察することができます。川匂などの農耕地に下りて餌をとることもあります。
- 全長:61センチメートル
- 科:サギ
- 種類:留鳥
アオサギ
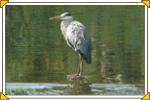
日本でもっとも大きいサギで本州から九州で繁殖し本州以南で越冬します。水田、湿地、河川、湖沼、干潟などで餌をとります。背面が青灰色で、頭は白く、側頭に黒い帯があります。夏羽では黒い冠羽が出ます。くびは灰色で、前頚に縦斑があります。グワーとかキャッという声で鳴きます。葛川や中村川の水辺で獲物を捕るところや岸近くの樹木の上にとまっているのを観察することがありますが、その数は少なく、1羽か2羽です。
- 全長:93センチメートル
- 科:サギ
- 種類:留鳥
カルガモ
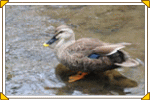
全国で繁殖し、本州以南では留鳥です。湖沼、池、川、水田、海岸などにすんでいます。雌雄同色で、ほかのカモのメスに配色が似ています。顔が淡色で黒線が2本あります。尻が黒く、三列風切の白色が目立ちます。
くちばしは黒く先端が橙黄色です。つばさの下面は白と黒に二分されており、飛んでいる時は目立ちます。
グェグェという声で鳴きます。中村川や葛川で普通に見られ、2羽から10羽前後の小群を形成していることが多くあります。
- 全長:61センチメートル
- 科:カモ
- 種類:留鳥
トビ

ハシブトガラスより大きく全身黒褐色で雌雄同色です。上空を帆翔(はんしょう)している時、尾をバチ形に広げ翼の先は指のように割れています。下面翼角の白斑がよく見えます。二宮海岸や吾妻山などのほか、町内各地に普通に生息しています。雑食性で魚の死体などを食べます。飛びながら、よく通る声でピーヒョロヒョロヒョロと鳴きます。
- 全長:オス58.5センチメートル、メス68.5センチメートル
- 科:タカ
- 種類:留鳥
オオタカ

幅の広い翼と長い尾を持ち、頭上、背、翼の上面、尾は暗青灰色で、尾羽には4本の黒い横帯があります。ほおは青黒色で白い眉斑(びはん)が明瞭、下面は白地に細い黒横斑が一面にあり、飛翔時によく見えます。北海道と本州の丘陵地から山地の林で繁殖し、秋から冬は全国の平地や低山の林にすみます。ギッギッと鳴きます。
主に冬期に吾妻山や一色周辺の林縁(りんえん)、中村川の上空を帆翔(はんしょう)しているのが見られます。早い羽ばたきと短い滑翔(かっしょう)を交互に行い直線的に飛びます。鷹狩りに使われてきたタカで、主な獲物は大小の鳥ですが、ネズミやウサギなども捕食します。
- 全長:オス50センチメートル、メス56.5センチメートル
- 科:タカ
- 種類:留鳥
キジバト

別名ヤマバトと呼ばれるように、もとは山地に生息していたのが市街地にも分布を広げたもので、もっとも普通に見られる野生のハトです。ブドウ色を帯びた灰褐色で翼にうろこ模様があります。首の青、白、黒の縞模様が目立ち雌雄同色です。公園や庭でも一年中見られ地上で餌を探しています。よく響く低い声でデデポッポーと繰り返し鳴きます。
- 全長:33センチメートル
- 科:ハト
- 種類:留鳥
カワセミ
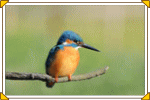
北日本では夏鳥ですが、本州南部以南では一年中いて、平地の水辺にすみます。大きさはスズメ位ですが、くちばしが長く丸っこい体なので大きく見えます。頭部から背、腰まで美しいコバルトブルーで、両ほおと胸、腹にかけては橙黄色で、のどと両えりは白色です。また、両翼の雨覆(あまおおい)にはブルーの斑点が規則的に散在しています。その美しい姿のため、探鳥会でもっとも人気の高い鳥の一つです。主に小魚をダイビングして捕え食べます。水辺の小枝などにとまり、水面をじっと覗きこんでいる姿を見ることがあります。
葛川ではほぼ全流域で普通に見られますが、下流よりも上流で、また冬期の方が見られるチャンスが多くなっています。中村川でも見られますが、以前より見られる機会が少なくなりました。
- 全長:17センチメートル
- 科:カワセミ
- 種類:留鳥
アオゲラ

日本固有のキツツキです。ハトほどの大きさで比較的細長い体形です。上面は黄緑色、下面は淡緑灰色で腹部には黒い横縞があります。
オスは頭の赤斑がよく目立ちます。吾妻山などの丘陵地や川勾神社の林で通年見られます。キツツキの仲間は木に縦向きにとまり波状飛行します。繁殖期にはくちばしで幹を叩いて、タラララララという音を立てます。これはドラミングとよばれています。口笛のような声でピョー、ピョーと鳴きますが、飛びながらアカゲラと同じようにキョッ、キョッと鳴くこともあります。
- 全長:29センチメートル
- 科:キツツキ
- 種類:留鳥
コゲラ
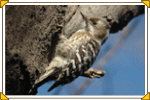
もっとも小さなキツツキです。上面は黒と白のまだら模様、下面は汚白色で雌雄同色です。よく茂った林にすみます。
通年に吾妻山や川勾神社東裏の林のほか各地の住宅地の木立でも普通に見られます。幹や枝をラセン状に上に移動しながら虫を探しています。波状飛行します。シジュウカラやメジロの群と一緒になって移動することもあります。きしむような声でギィーッと鳴きます。
- 全長:15センチメートル
- 科:キツツキ
- 種類:留鳥
セグロセキレイ

ハクセキレイと同じ祖先から出発して大陸で両者分化し、日本へはハクセキレイよりも早く侵入したものらしく、すでに大陸にはセグロセキレイがいません。この結果セグロセキレイは日本固有の種となりました。九州以北では留鳥で、石の多い川原で普通に見られます。顔とほほが黒くまゆは白くなっています。飛ぶと白いつばさが目立ちます。ジジッジジッというにごった声で鳴きます。ジービジチチロジージジなどと美しく歌います。中村川や葛川で普通に見られますが夏期には少なくなります。また、冬期には川匂の農耕地や畑地などでも見られます。
- 全長:21センチメートル
- 科:セキレイ
- 種類:留鳥
ヒヨドリ

尾が長くスマートな体形です。全体は灰褐色、頭部、翼、尾は青灰色で、ほおは茶褐色です。度々短い冠羽を立てますので頭がギザギザに見え雌雄同色です。一年中林のほか公園や庭などで最も普通に見られる鳥です。深い波状飛行をします。
繁殖期には昆虫をよく食べますが、それ以外の季節は木の実を食べます。また、花の蜜が好きで、群でサクラの樹を渡っていったり、ツバキの花にくちばしを突っ込み花粉で顔を黄色くしていたりするのをよく見かけます。よく通る声でヒーヨ、ヒーヨとやかましく鳴きます。ピョー、ピョーと口笛の様にアオゲラに似た声でもよく鳴きます。
- 全長:27.5センチメートル
- 科:ヒヨドリ
- 種類:留鳥
モズ

頭部が大きく猛禽類特有の先の曲がった短いくちばし、尾は長めです。オスは黒い過眼線(かがんせん)があり、背と尾は青灰色、翼は黒くなっています。メスは全体が茶褐色をしています。浅い波状飛行をします。秋から春にかけて丘陵地や住宅地付近でもよく見られます。尾をグルグル回します。かん高い鋭い声でキィーキィキィキィと鳴き「モズの高鳴き」といわれています。また、昆虫やカエルなどを枝やトゲに刺す習性があり「モズのハヤニエ」といわれています。
- 全長:20センチメートル
- 科:モズ
- 種類:留鳥
イソヒヨドリ
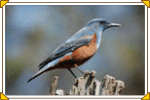
全国の磯や浜などにすみ、林に入ることは稀ですが、近年は内陸部の市街地で観察することが多くなりました。オスは青と赤茶の綺麗な色、メスはヒヨドリに似た地味な色で、尾は短く、ふわふわした感じでゆっくり飛びます。ジジッと鳴き、岩や人家の屋根にとまってツツピーコーとオス・メスとも美しい声で歌います。
二宮海岸の突堤、葛川や中村川の堰堤や橋の下、あるいは周辺の人家の屋根の上に乗っているところを見ることがあります。二宮駅南口のビルや百合が丘の人家で毎年子育てしていることも確認されています。
- 全長:26センチメートル
- 科:ツグミ
- 種類:留鳥
ウグイス

いわゆるウグイス色ではなく全体にオリーブ褐色ですが、腹側と眉斑(びはん)は淡い色をしています。尾は長めでオスはメスより大型です。からだを水平にして枝に止まり体を左右に活発に振りながら枝移りしますが、ササなどのやぶの中にいて、あまり姿を見せません。よく通る美しい声でホーホケキョとさえずるほか、ケキョ、ケキョ、ケキョ・・・と長く繰り返して鳴き、「谷渡り」といわれています。地鳴きはチャッ、チャッと濁った声で鳴き、「笹鳴き」といわれています。
- 全長:13.5から16センチメートル
- 科:ウグイス
- 種類:留鳥
ヤマガラ
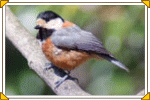
胸から脇腹が赤茶色、翼は青灰色でほおがクリーム色をしたカラ類です。
雌雄同色です。留鳥ですが二宮町では主として冬期に吾妻山などの樹林帯で見られ、住宅街の庭にも来ますが数は多くありません。シジュウカラやメジロなどと混群をつくって移動することもあります。カラの仲間は枝等に止まっている時に始終左右に身体を振り警戒しています。また、木の実を両足にはさみ器用に中味をほじくり出して食べます。尻上がりにツツビー、ツツビーとさえずります。
2011年1月「二宮町の鳥」に制定されました。
- 全長:14センチメートル
- 科:シジュウカラ
- 種類:留鳥
シジュウカラ

背は緑灰色、翼と尾はグレイで、頭部は黒く後頭部に白い縦斑があります。胸から腹にかけて通る、ネクタイのような太い黒色の縦斑と白いほおが目立っています。雌雄同色です。明るい林にすみ、通年に吾妻山や百合が丘など木の多い住宅地でもよく見られます。巣箱をよく利用します。ヤマガラより少し早いテンポでツツピー、ツツピーとさえずります。地鳴きはツッチーとかジュクジュクと鳴きます。
- 全長:14.5センチメートル
- 科:シジュウカラ
- 種類:留鳥
メジロ

上面は黄緑色、下面は汚白色、目の周りにハッキリとした白いリングがあり、のどは黄色で雌雄同色です。二宮町では晩秋から春にかけ丘陵周辺で見られるほか庭にもよく来ます。地上に降りることは稀です。虫や木の実を食べますが、花の蜜が好きでヤブツバキやサクラなどの花に群がって蜜をよくすっています。高い声で細やかにチーチュル、チーチュルとかチチル、チチル、チュルチーなどとさえずり、「長兵衛、忠兵衛、長忠兵衛」と聞きなされています。地鳴きはチー、チーと鳴きます。
- 全長:11.5センチメートル
- 科:メジロ
- 種類:留鳥
ホオジロ

上面が茶褐色で黒い縦斑、顔はオスが黒と白、メスは褐色と白のしま模様があります。胸は赤褐色をしています。吾妻山周辺、百合が丘ほか各地の林縁で見られます。木のこずえで上を向いて胸を反らして張りのある奇麗な声でチッチーピッ、ツチチ、ツツピーなどと複雑なさえずりをします。「一筆啓上仕り候」、「源平つつじ、白つつじ」の聞きなしがあります。
- 全長:16.5センチメートル
- 科:ホオジロ
- 種類:留鳥
カワラヒワ

全身オリーブ褐色で、飛ぶと翼の黄色い翼帯が目立ちます。くちばしは太めで肉色をしています。オスは頭部の黄緑色が目立ちますが、雌雄同色です。はずんだ声でキリリ、コロロとさえずり、時々「ビィーン」という濁った声をまじえます。
主に冬期に吾妻山、葛川や中村川流域の畑地などで普通に見られ、群をなして地上で草の種子などを食べています。吾妻山では時に80から100羽ほどの群をつくって、にぎやかに鳴きながら樹冠を移動していくことがあります。
- 全長:15センチメートル
- 科:アトリ
- 種類:留鳥
ムクドリ

尾は短かめですが比較的スマートな体形です。全体に黒褐色で頭部は黒色、腰は白くなっています。顔は黒褐色で、くちばしの基部から放射状に白の縦縞模様があり雌雄同色です。
オレンジ色のくちばしと足が目立ちます。ほぼ一年中吾妻山周辺や中村川、葛川流域のほか住宅街でも見られ、群になって地上を歩いて餌を探しています。少し濁った声でギュウ、ギュギュと鳴きます。
- 全長:24センチメートル
- 科:ムクドリ
- 種類:留鳥
サシバ
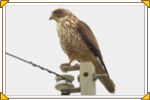
雌雄同色で、上面は茶褐色、下面は白に褐色の横斑、のどの中央には黒い縦斑があり、白い眉斑が目立ちます。飛翔時、翼の先は指のように割れて、尾に数本の黒い横帯が見えます。夏鳥として渡来し、低山、丘陵の林などで繁殖し、谷戸田のような開けたところで狩りをし、ヘビ、トカゲ、カエルなどを捕食しますが、小鳥を襲うこともあります。飛びながらピッークィ、ピッークィと鳴きます。
9月末から10月中旬の渡りの時期には、群をつくって西へ移動していく様子を吾妻山の展望台や町北部の丘陵地で見ることができます。
- 全長:オス49センチメートル、メス51センチメートル
- 科:タカ
- 種類:夏鳥
キアシシギ

旅鳥として干潟、岩礁、川岸、水田などに渡来します。上面が一様に灰褐色で、脚は汚黄色で短めの地味な鳥です。夏羽では胸から脇にかけて波状の横縞があり、腹は白い。冬羽では下面の横縞がなくなり、胸から脇は灰色です。ピュイーという声で鳴きます。
毎年、春秋の渡りの時期に葛川や中村川で見られますが、数は多くありません。
- 全長:25センチメートル
- 科:シギ
- 種類:旅鳥
アオバト

キジバトより少し大きく、全体に緑色で腹は白っぽく、雌雄同色ですが、オスは雨覆の羽のブドウ色が鮮やかです。主に夏鳥で、山地のよく茂った林にすみ、尺八を吹くような風変りな声でアーオー、アーオーと、もの悲しげな声で鳴きます。海水や温泉の水を飲むハトとして知られていますが、その生態は明らかになっていません。
大磯の照ヶ崎海岸は、5月から11月頃までアオバトが海水を飲みにくる場所として有名ですが、二宮でも、主に春と秋の渡りの時期に吾妻山やテトラポットのある海岸へ数羽の群でやってきます。
- 全長:33センチメートル
- 科:ハト
- 種類:夏鳥
ツバメ
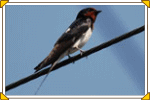
二つに割れたいわゆる燕尾をしたスマートな体形です。頭部から尾までは光沢のある暗紺色、下面は白、のどと額が暗赤色で雌雄同色です。夏鳥として渡来し、二宮町では3月中旬頃から市街地などで普通に見られます。人家の軒下などにおわん型の巣をつくります。低空で高速に飛びながら虫を捕えます。ヒバリによく似た声でチョリ、チョリ、ピリリリと鳴きます。
「土食って虫食ってシブーイ」という聞きなしがあります。
- 全長:17センチメートル
- 科:ツバメ
- 種類:夏鳥
イワツバメ

羽や尾がツバメよりやや短く切り込みが浅くなっています。上面は光沢のある黒、腰は白く飛翔時にもよく目立ちます。下面は白で雌雄同色です。夏鳥として渡来し、吾妻山の上空をヒラヒラと飛んでいるのを見かけます。ビルの軒下や橋桁の内側に小さな入口のあるおわん型の巣をつくります。はやいテンポでジュッ、ジュッと濁った声で鳴きます。
- 全長:14.5センチメートル
- 科:ツバメ
- 種類:夏鳥
キビタキ

オスは眉(まゆ)と胸、腰が黄色く、黒い背とのコントラストが美しい鳥です。両翼の白斑もよく目立ちます。メスは全体がオリーブ色で他のヒタキ類と見分けにくいかもしれません。夏鳥として渡来して、吾妻山周辺で見られるほか川勾神社の林、一色のうさぎ沢など、林内に空間のある広葉樹林で見られます。奇麗な声でピチュリ、ピィ、ピピリと複雑にさえずります。
- 全長:13.5センチメートル
- 科:ヒタキ
- 種類:夏鳥
オオルリ

オスは体の上面は濃い黒青色で額から頭頂にかけては光沢のある青色、ほおからのど、胸、脇腹は黒く、腹は白い美しい鳥です。ウグイス、コマドリとともに日本三鳴鳥(めいちょう)といわれます。メスはキビタキのメスに似ていますが、やや大きく上面は茶褐色でのどと腹部ははっきり白い。夏鳥として渡来し、谷ぞいのよく茂った林を好んですみます。
二宮町では毎年4、5月頃に吾妻山にやってきて、高い木の上でピーリーポピヒーリー、ジジッーリージジッと美しい声で囀ります。一色のうさぎ沢や桜美園周辺の林での観察記録もあります。
- 全長:17センチメートル
- 科:ヒタキ
- 種類:夏鳥
エゾビタキ
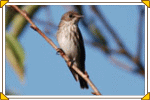
スズメほどの大きさでコサメビタキよりやや大きい。雌雄同色で、頭から背、尾は灰褐色で、白っぽい胸には明瞭な黒い縦斑があります。
旅鳥として9月下旬から10月上旬に低地から低山の林に渡来し、吾妻山や一色の山林で見られますが、数は多くありません。ミズキの実を好み集まりますが、梢や枯れた枝先など目立つところに出ることが多い鳥です。地鳴きは鈍い声でジィとかツィーと鳴きます。
- 全長:15センチメートル
- 科:ヒタキ
- 種類:旅鳥
マガモ
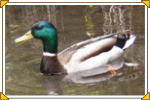
主に冬鳥として湖沼、池、川、海岸などにやってきます。オスの体は灰色で、頭から首にかけて黒緑色、胸は褐色で白い首輪があります。メスはくちばしの中央部が黒く、周辺部が橙色で尾が白くなっています。オスはその独特の色模様から「アオクビ」とも呼ばれます。
冬期に葛川や中村川で普通に見られますが、数は少なくせいぜい2、3羽から5、6羽といったところです。二宮高校裏の打越川でも見られることがありますが稀です。
- 全長:59センチメートル
- 科:カモ
- 種類:冬鳥
コガモ
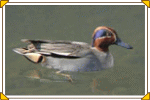
主に冬鳥として全国の湖沼、池、川、海岸などに渡来します。
オスは頭部が栗色で緑色帯があり、灰色の体に水平の白線が出ています。メスはこれといった特徴がありません。冬期に葛川や中村川のほぼ全域で見られます。葛川では、萬年橋の下流側で30から40羽の群が、中村川では、新幹線鉄橋の下流側や白髭神社横あたりで多く見られます。オスは「ピリッ」、メスは「グエッ」と鳴きます。
- 全長:38センチメートル
- 科:カモ
- 種類:冬鳥
ノスリ

胸から腹は黄白色で脇に褐色部分があり、翼の下面は淡褐色で、下面翼角の黒色斑が目立ちます。頭部は淡褐色に黒褐色の縦斑があり、クリクリした優しい眼をしています。雌雄同色です。帆翔(はんしょう)時、翼の先は指のように割れて見えます。低山で繁殖しますが冬期には全国的に平地や住宅街の公園などでも見られます。冬期に吾妻山周辺、中村川流域、一色周辺などの林縁や農耕地で普通に見られますが、百合が丘、川匂農道周辺の上空でも見かけます。
停空飛翔(ていくうひしょう)と降下を繰り返してネズミ、小鳥などを捕食します。ピーエー、ピ―エーまたはピョー、ピョーと鳴きます。
- 全長:オス54センチメートル、メス57センチメートル
- 科:タカ
- 種類:冬鳥
ユリカモメ
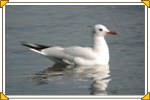
冬鳥として海岸、川、湖沼に渡来します。背面が淡青灰色なので体が白っぽく見え、くちばしと脚が赤いカモメです。頭部は夏羽では黒褐色、冬羽では白くて眼の後ろに黒褐色斑があります。飛ぶと初列風切(しょれつかざきり)の先端が黒い線になり、翼を閉じると先が黒一色になります。
冬期に二宮海岸沖の定置網の浮にとまったり、海上を飛んでいたりすることがあります。また、稀に中村川の上空を飛ぶ姿を見ることもあります。
- 全長:40センチメートル
- 科:カモメ
- 種類:冬鳥
ハクセキレイ

関東以北と中国、九州で繁殖します。冬には根雪の少ない地方で普通に見られ、水辺に近い開けた土地を好みます。
顔は白く頭部と胸は黒色で、目の前後にだけに黒く細い横すじ(過眼線(かがんせん))があり、飛ぶと白いつばさが目立ちます。冬の間は全体に淡い色で、夏の間黒色だった背も、冬にはねずみ色に変化しています。キセキレイやセグロセキレイよりやさしく、チュチュッ、チュチュッまたはチュィリー、チュィリーと鳴きます。中村川や葛川で普通に見られ、セキレイ類の中ではもっとも多く見られますが夏期には少なくなります。また、冬期には川匂の農耕地や畑地などでも見られます。地鳴きは「チチッ、チチッ」です。
- 全長:21センチメートル
- 科:セキレイ
- 種類:冬鳥
ルリビタキ

スズメほどの大きさで、オスの背は光沢のある瑠璃(るり)色で、翼は黒く、腹側は濁白色で脇はオレンジ色の美しい鳥です。メスは背中がオリーブ色で尾羽だけが瑠璃色です。漂鳥(ひょうちょう)で、春から秋にかけて山地にすみますが、冬期には低地や暖地へ移動します。
冬期に吾妻山周辺で普通に見られ、一色のうさぎ沢や川勾神社周辺などのよく茂った林でも見られます。
- 全長:14センチメートル
- 科:ヒタキ
- 種類:冬鳥
ジョウビタキ
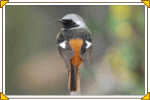
オスは頭が銀色で、頬から喉にかけての黒色と胸のオレンジ色がよく目立ちます。メスは全体に灰褐色です。オス・メスともに翼の白斑が目立ち、「紋つき鳥」と呼ばれます。冬鳥として二宮町には10月20日前後に渡来し、吾妻山や林縁、公園など開けた場所で普通に見られ、住宅地の庭などにもよく来ます。おじぎをするように頭をさげ尾をふるわせます。低い声で短く切って、カッカッ、カッとかヒッ、ヒッとつぶやくように鳴きます。
- 全長:14センチメートル
- 科:ツグミ
- 種類:冬鳥
シロハラ

雌雄同色で、頭から尾にかけては茶褐色、腹は淡褐色で白っぽく見えます。飛び立つ時に尾の先端両側の白斑がよく目立ちます。冬鳥として丘陵地の暗い林に渡来し、吾妻山周辺で普通に見られるほか、山西や一色の林でも見られます。習性はアカハラによく似ていますが、アカハラのように明るい場所に出ることはなく、林の中にいることが多いので見つけにくい鳥です。
地鳴きはアカハラに似てキョッ、キョッ、キョッと鳴き、渡去前にはキィチョロリー、キィチョロリーと囀(さえず)ることがあります。
- 全長:24センチメートル
- 科:ツグミ
- 種類:冬鳥
ツグミ

上面は褐色、翼は黒褐色と茶褐色、下面は白地に黒いうろこ状の斑点模様がハッキリ見えます。淡黄白色の眉斑(びはん)があり雌雄同色です。冬鳥として11月中旬に渡来し、吾妻山などの林や各地の農耕地などで普通に見られます。地上を両足をそろえてピョンピョンと歩きながら餌を探し、時々立ち止まって胸をそらせたポーズをとります。地鳴きは小さな声でグヮッ、グヮッと鳴きます。
- 全長:24センチメートル
- 科:ツグミ
- 種類:冬鳥
アオジ

上面は緑灰色に黒い縦斑、下面は黄緑色で胸から脇に黒い縦斑があり雌雄同色です。漂鳥です。標高1000m程度の林、林縁で繁殖し、冬期には低地、暖地に移動します。冬から早春に吾妻山や各地の林縁で普通に見られます。地上の木陰で草の実などを食べています。美しいゆったりとした声でピー、ピー、チュルリーとさえずります。地鳴きは「ヂッ」と少しにごり強い声です。
- 全長:16センチメートル
- 科:ホオジロ
- 種類:冬鳥
ウソ

少々ズングリした体形に太めの短いくちばしが特徴の鳥で、頭部、翼、尾は黒く、背中は灰色で腰は白い。オスはのどとほおが赤く、メスは黒い部分のほかは全体に灰褐色の地味な色です。漂鳥で、亜高山帯で繁殖し冬期には標高の低い山地や暖地へ移動します。
低い口笛のような声でフィッ、フィッと短く静かに鳴き、飛ぶ時は羽状飛行します。
二宮町では1月から3月にかけて吾妻山などでサクラの花芽を啄(ついば)んでいるのを見かけることがありますが、年によって飛来数にバラツキがあります。
- 全長:16センチメートル
- 科:アトリ
- 種類:冬鳥
シメ

ずんぐりした体形に太いくちばしの鳥です。頭部は褐色、背は暗褐色で下面は淡褐色、目先と喉は黒く、くちばしは淡灰褐色で夏には鉛色になります。青黒色の翼の白斑が波状飛行時にもよく目立ち雌雄同色です。北海道の低地や山地で繁殖し、冬期には暖地に移動します。冬期から春にかけて低地の明るい林や吾妻山で見られます。
単独でいることが多く群で行動することはまれです。太いくちばしで木の種子を割って中身だけを上手に食べます。
ほとんどさえずりませんが、ツチッ、ツチッと細い声で鳴きます。
- 全長:18センチメートル
- 科:アトリ
- 種類:冬鳥
お問い合わせ
二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班
住所: 〒259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
電話: 0463-72-6912
ファクス: 0463-72-6914
