梅沢前原遺跡
- [更新日:2025年9月30日]
- ID:65
このページでは梅沢前原(うめざわまえはら)遺跡についてご紹介します。
梅沢前原遺跡は神奈川県中郡二宮町山西の梅沢字前原に位置し、町立体育館の建設に伴う工事の最中に発見されました。相模湾を臨む海蝕台地上に発達した砂丘内にあり、標高は19.7メートルほどあります。発掘調査の第1回目は1984年(昭和59年)11月より12月、第2回目は宅地造成工事にともない1986年(昭和61年)3月から4月にわたって実施されました。
第1回目の調査では発掘面積は約60平方メートルの中に重複して存在する8基の竪穴住居址を確認し、土器片(土師器)や一部鉄製品を採集できました。
土師器の種類を分析した結果、古墳文化前期の五領式期と平安朝期の国分式期のものとがありました。これは二つの時期の遺跡が重複して存在していることになります。
古墳時代は3世紀の中ごろにあたりますので、1750年ほど前から現在まで人間が住み続けている場所であることがわかります。

口周り14.5センチ、胴回り15.6センチ、高さ13.2センチあり、一部復元されています。
第1回目の調査の際に竪穴住居内より発見されました。
器の表面をよく見ると、櫛でとかしたような細かな線が引かれているのがわかります。器の内外には赤い塗料が塗られています。
横から見たところ
上から見たところ

一見するとすり鉢型の器のように見えます。
本来は逆さに置いてこの台の上にかめが付いています。
第1回目の調査の際に竪穴住居内より発見されました。
台の裾の長さは15センチあり、かなり大形のかめを乗せていたことがわかります。
写真2枚目は台を逆さにして上から見たところです。
これをみると底に黒ずんだ跡が残っていることが分かります。
もしかすると古墳時代に壊れていた器を後から拾ってすり鉢として再利用したのかもしれません。
横から見たところ
上から見たところ
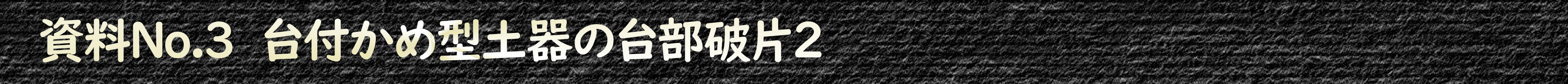
資料ナンバー2と同じものですが、こちらは小型です。
全体に櫛でとかしたような細長い線が付けられています。
手ひねりで作ってありますので、形が少々いびつです。

これはかめのような丸い器を下で受けるための土器です。
つぼ置き台とでもいうのでしょうか。丸いかめを地面に置く場合、不安定になって転んでしまうので、この台の上に置きます。
滑り止めのためか、置く部分には細い線がひかれています。残念ながら大きく欠けてしまっています。

残念ながら口の部分しか残っていません。口の広さが20センチほどあることから、わりと大型のつぼであったことがわかります。
この口は折り返し口と言われ、粘土がまだ軟らかいときに外側にめくり上げてくっつけてしまいます。
こうするとつぼの口にでっぱりが付くので運びやすくなるほか、口が欠けにくくなります。

所在地
山西字前原
遺跡種別
集落址
時代
古墳~奈良・平安
概要
1984年、町立体育館建設に伴う発掘調査。古墳時代前期、平安時代の集落跡を検出。
土師器などが出土。
参考文献
梅沢前原遺跡発掘調査団 1986『梅沢前原遺跡』二宮教育委員会
梅沢前原遺跡発掘調査団 1991『梅沢前原遺跡2.』二宮教育委員会
お問い合わせ
二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班
住所: 〒259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
電話: 0463-72-6912
ファクス: 0463-72-6914
