山西地区の文化財
- [更新日:2025年9月22日]
- ID:36
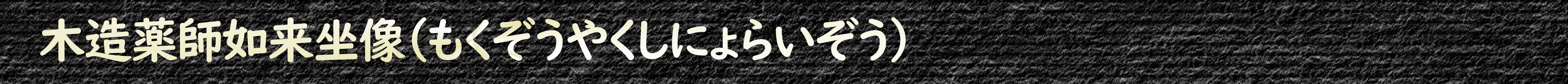
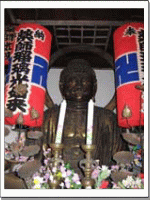
二宮町指定 重要有形文化財 昭和49年6月指定
かつては川勾神社の本地仏でしたが、明治時代の神仏分離令により別管理となりました。
現在は、茶屋の薬師堂に安置されています。
像高は261.5センチとかなり大きく、寄木造り・彫眼・漆箔で、江戸時代の作です。毎年4月12日には薬師の供養祭があります。
また、毎月12日にはお年寄りたちが薬師堂に集まり、念仏を唱えています。
所在地/保管場所:二宮町山西551 茶屋薬師堂

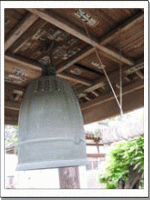
二宮町指定 重要有形文化財 昭和49年6月指定
もとは吾妻神社の別当坊千手院にあったものを明治時代に移しました。
高さ101センチ、口径60センチあります。
寛永8年(1631年)の銘より、町内に現存する最古の梵鐘であることがわかりました。
「別当等覚院 頼栄」、「禰宜并本願 内海右近尉定房」「大工 青木源右衛門尉(小田原住)」の名が読み取れます。
音は澄みきっていて、遠くまでよく響きます。
所在地/保管場所:二宮町山西793 等覚院

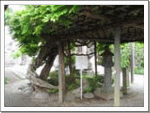
二宮町指定 史跡名勝天然記念物 昭和49年6月指定
境内にあるフジの木は、推定樹齢・約400年とされています。
花は紫白の二色あり、毎年4月の半ば頃に咲きます。
1660年頃、仁和寺の宮が関東に下向した際に当寺へ立ち寄り、藤の花の美しさをめでて「藤巻寺」の別号を与えました。
所在地/保管場所:二宮町山西793 等覚院
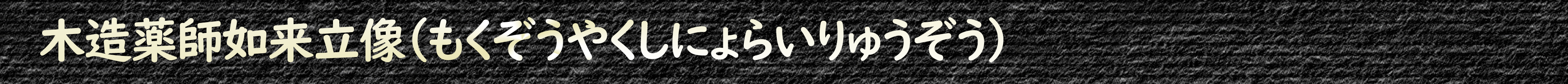
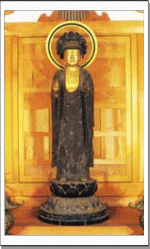
境内西側にある薬師堂に祀られているこの像は、亨禄5年(1532年)の銘の残る大変古いものです。
高さは1.3メートルほどで、穏やかな表情をしています。
寄木で造られ、玉眼が入っています。
所在地/保管場所:二宮町山西793 等覚院
現在、公開しておりません。

二宮町指定 史跡名勝天然記念物 昭和58年4月指定
このタブの木は町内最大の古樹(推定樹齢300年)です。国道一号線沿いにあり、通る人に安らぎと潤いを与えてくれます。
タブの木は生活資材としての利用度が低いことから伐採されるのが一般的です。
しかし木の下には祠がまつられ、信仰の対象となっていることから、長い間大切に守られてきたことがわかります。
所在地/保管場所:二宮町山西191 松本家
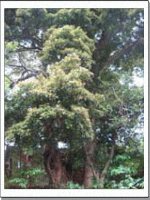
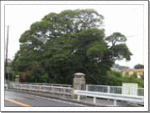


板碑とは中世武蔵秩父方面を中心に建てられたもので、この板碑も「武蔵型板碑」の系統です。主に祖先の供養や墓石として建てられます。板碑には嘉暦2年(1327年)の銘があり、高さは76センチあります。中世の石造物として代表的なものといえます。
現在、公開しておりません。
管理者・所有者の希望により、所在地と保管場所の表示を控えさせていただきます。


このお寺の境内にある石祠は、「おしゃもじさん」と呼ばれ、子どもの虫封じに験があります。
祠の中には子どもの名前や生年月日を書いたしゃもじがたくさん奉納されています。
現在、公開しておりません。
管理者・所有者の希望により、所在地と保管場所の表示を控えさせていただきます。
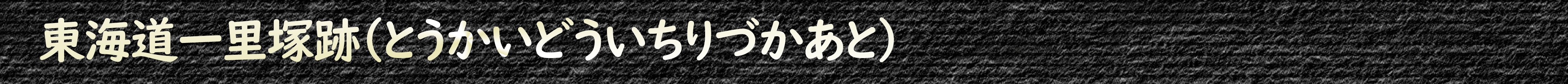

茶屋の押切坂付近にある一里塚は江戸日本橋から18番目にあたり、かつては街道を挟んで両側に築かれていました。
塚の上にはニレ科の落葉樹である榎(南側)と槻(北側)が植えられていました。
一里塚周辺は旅人目当ての茶屋や商店が軒を並べる「梅沢の立場」として大変賑わっていました。
所在地/保管場所:二宮町山西554-2

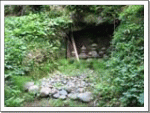
「やぐら」は中世鎌倉地方に見られた典型的な墓地の形態です。
二宮のやぐらは昭和54年道路整備中に発見されました。
中世の祭祀用と思われる「かわらけ」の破片等も合わせて出土し、内部奥壁に沿って7基の五輪塔が並んで立っています。
現在、公開しておりません。
管理者・所有者の希望により、所在地と保管場所の表示を控えさせていただきます。

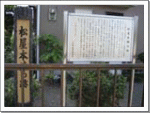
和田家は、江戸時代、大磯から小田原両宿の間の宿として御休本陣を賜りました。
当主は代々、松屋作右衛門と名乗りました。
こちらに保管されている「御休帳」は、本陣に立ち寄った大名や旗本などの記録で、大変貴重な資料です。
所在地/保管場所:二宮町山西410 和田家
(注釈)現在、資料は生涯学習センターで保存していますが、公開しておりません。
お問い合わせ
二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班
住所: 〒259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
電話: 0463-72-6912
ファクス: 0463-72-6914
