二宮地区の文化財
- [更新日:2025年9月22日]
- ID:44

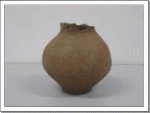
二宮町指定 重要有形文化財 昭和49年6月指定
昭和47年(1972)に秋葉山の宅地造成工事の際、発見されました。
高さ16センチ、中央周囲51センチあり、素焼きの上に朱泥(しゅでい)がぬられ3段の輪積みで製作されたものです。
首部が破損しているため、全体の形はわかりません。
所在地/保管場所:二宮町二宮1240-10
生涯学習センター地下特別収蔵庫
現在、公開しておりません。

二宮町指定 重要有形文化財 昭和50年9月指定
梅沢御本陣と呼ばれる旅籠の松屋は旧東海道に面し、大名・幕府役人・公家等の休憩所にあてられていました。
営業記録簿として書き留めていた宝永5年(1709年)からの御休帳のほか、諸大名帳、御定宿帳・書状図面などが町の重要有形文化財に指定されています。
内容の詳細は『梅沢御本陣』(二宮歴史研究会・二宮町教育委員会発行、平成5年2月)にまとめられています。
所在地/保管場所 : 二宮町二宮1240-10
生涯学習センター地下特別収蔵庫
現在、公開しておりません。

萬年氏は徳川氏の家臣で、遠江(とおみ)川尻村に居を構え、東照宮にも仕えました。
その後、二宮の代官となり、萬年堰を作ったほか、数多くの功績があります。二宮の住まいは「萬年屋敷」と呼ばれていました。
現在、公開しておりません。
管理者・所有者の希望により、所在地と保管場所の表示を控えさせていただきます。
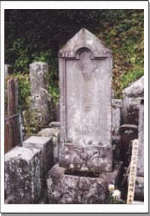
萬年重頼の墓
(明暦元年・1655年建立)
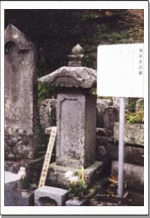
萬年頼隆の墓
(建立年不詳)
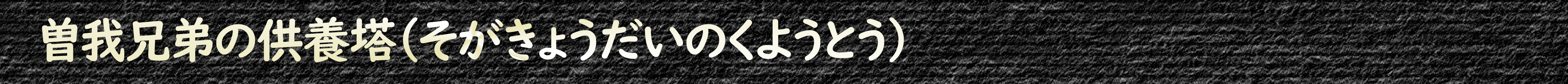
曽我兄弟は父の仇、工藤祐経を討って永年の本懐を遂げました。
兄弟には土地の豪族二宮朝忠に嫁いだ姉がおり、姉は出家して花月尼と称し、兄弟の菩提(ぼだい)を弔いました。
所在地/保管場所:二宮町二宮1091 知足寺

曽我五郎の供養塔
(元禄7年・1694年建立)

曽我十郎の供養塔
(元禄7年・1694年建立)
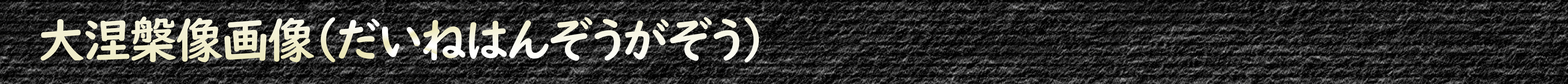
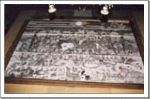
天保年間(1830~1844年頃)に本寺22代目の住職が京都から狩野派の絵師を頼んで写させたものです。
原画は東福寺所蔵のもので、このことは本寺所蔵の資材帳に記録されています。
所在地/保管場所:二宮町二宮1514 龍澤寺
現在、公開しておりません。

第2次世界大戦中の昭和20年8月、東京から疎開していた高木敏子さんは二宮駅で空襲に遭い、父を失います。
後に高木さんは悲惨な戦争体験をつづった『ガラスのうさぎ』を出版しました。
この像は昭和56年、永遠の平和を願う大勢の人々の浄財によって建てられました。
所在地/保管場所:二宮町二宮838 二宮駅南口

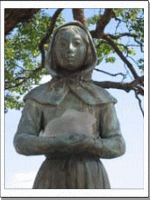
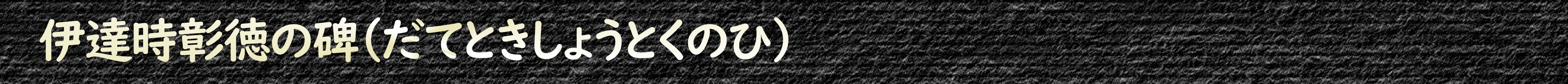

明治維新以降、この地域の発展と社会福祉活動に功績のあった一人に伊達時がいます。
伊達時は二宮駅の開設や秦野―二宮間の交通網の整備、郷土の子どもたちの教育に尽くしました。
この碑は昭和26年に伊達の功績を永く後世に伝えるため、町民有志により建てられました。
所在地/保管場所:二宮町二宮838 二宮駅南口


中町のカトリック教会西側の海岸に向かう小道に祠があります。
この祠は、江戸時代に海難事故で亡くなった人の供養のために、その家族からのお礼で建てられたといわれています。
以来、水難・海難に限らず、災難除けの観音さんとして祈願する人が訪れています。
所在地/保管場所:二宮町二宮88付近

毎年5月5日に大磯町国府で行われる国府祭(こうのまち)で、川勾神社の神輿が神揃山(かみそりやま)へ行って神事を行い、帰りに立ち寄るのがこのお旅所です。
原家では昔からの伝統で、神輿をウスの上に置いてもてなします。
所在地/保管場所:二宮町二宮268 原家
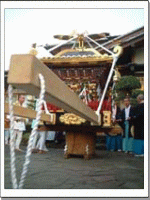

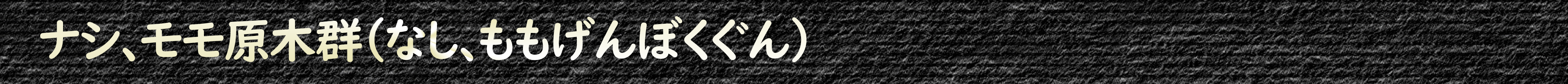

神奈川県指定 天然記念物 昭和47年7月指定
国のナシ・モモの果樹育成の歴史的研究天然記念物として、昭和初期に育成されたナシとモモの原木が保存されています。
主な種類として次のようなものがあります。
ナシ…菊水、新高、二宮白梨、相模、青龍、祇園、玉翠、旭
モモ…白鳳(現在は枯死)
所在地/保管場所:二宮町二宮1217
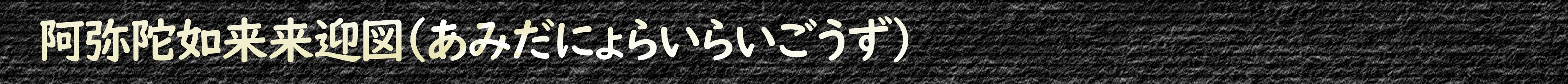
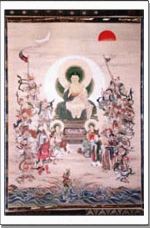
絵の背面に残された記述によると、文政11年(1828年)に天寧山龍澤寺に奉納されたことがわかります。
阿弥陀如来が来迎するさまが微細な描写で描かれています。
所在地/保管場所:二宮町二宮1514 龍澤寺
現在、公開しておりません。

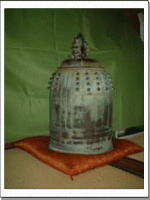
こちらの半鐘は元禄9年(1696年)に作られたもので、寺院で行われる諸行事の開始を知らせるために使われていましたが、第二次大戦中には軍需物質調達のため供出されました。
しかし、当時の平塚の消防署の半鐘の鳴りが悪かったことから、知足寺の鐘と取り替えられ、砲弾にならずに終戦となりました。
戦後は平塚の町で火災発生を知らせてきましたが、昭和39年(1964)に旧庁舎取り壊しの際、市の消防本部海岸出張所へ移され、昭和48年(1973)に元の場所である知足寺へ返されました。
所在地/保管場所:二宮町二宮1091 知足寺

文化12年(1815年)に出来上がったもので、鳳凰などの見事な彫刻が施されています。
所在地/保管場所:二宮町二宮1091 知足寺
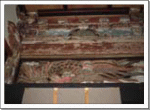
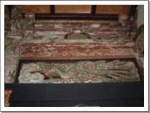

本堂に掛けられた百万遍念仏の大数珠は、安政4年(1857年)に作られたもので、珠の数は1272個、長さは約28mです。
珠には奉納者の名前、地域、願い事が刻まれており、二宮町の範囲はもちろん、平塚・秦野・小田原・箱根・品川など、広い地域から奉納されています。
この百万遍念仏の数珠は今でも知足寺のお十夜という行事で、檀家さんが念仏を唱えながら回します。
所在地/保管場所 : 二宮町二宮1091 知足寺
お問い合わせ
二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班
住所: 〒259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
電話: 0463-72-6912
ファクス: 0463-72-6914
