川匂地区の文化財
- [更新日:2025年9月22日]
- ID:39


二宮町指定 重要有形文化財 昭和49年6月指定
大正4年5月に水田発掘の際に発見されたものです。
奈良時代以前のもので、田植えの際に苗を運ぶため使われたと推定されています。
発掘された場所は川勾神社より西に2キロほどの、旧神領地(かつて川勾神社のあったところ)です。
半分に割れた形で、その片方だけが見つかっています。
所在地/保管場所:二宮町山西2122 川勾神社
現在、公開しておりません。

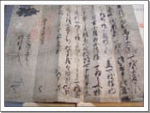
二宮町指定 重要有形文化財 昭和49年6月指定
川勾神社には戦国から江戸時代にかけての古文書が数多く伝えられています。
例えば、小田原北条氏から賜(たまわ)った虎朱印判状(こしゅいんばんじょう)は、元亀(げんき)3年(1572年)、約400年前に差し出されたものですが、現在でも朱の印が色鮮やかなまま保存されています。
川勾神社と武家とのかかわりの一端を示す史料群といえます。
所在地/保管場所:二宮町山西2122 川勾神社
現在、公開しておりません。
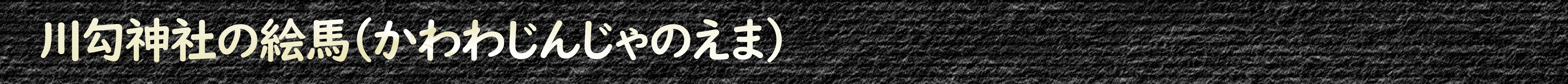
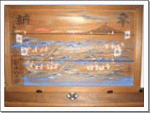
川勾神社には数多くの絵馬がありますが、その一つ、大正時代のキハダマグロ漁の様子を描いた絵馬は、梅沢の漁師が大漁の御礼に奉納したものです。
舟4艘(そう)と網にかかったたくさんの魚、右上には伊豆大島も描かれています。
漁で賑(にぎ)わっていた頃の二宮をうかがい知ることのできる貴重な資料です。
所在地/保管場所:二宮町山西2122 川勾神社
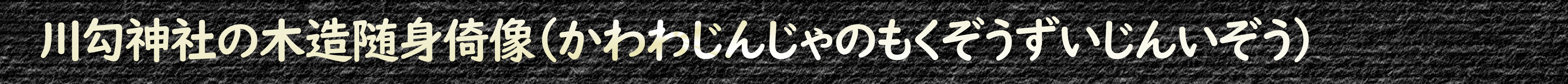
二宮町指定 重要有形文化財 平成19年3月指定
随身像は門前に置かれ、外から悪いものが入ってこないよう神様を守護します。
二宮川勾神社縁起書(えんぎしょ)によると、応永(おうえい)年間(室町時代中期)の戦乱で神殿や宝蔵(ほうぞう)等が焼失した際に、運良く難を逃れたとされています。
この像は随身像としては県下における一木(いちぼく)造りの現存最古であり、平安時代後期の古風な姿を残す大変貴重な像であることがわかっています。
また、彫刻には向かない節の多い広葉樹を使って作られていることから、お宮にあった神木を使って作ったのではないかと推測されています。
現在は随身門に安置されており、ガラス越しに見ることが出来ます。
所在地/保管場所:二宮町山西2122 川勾神社


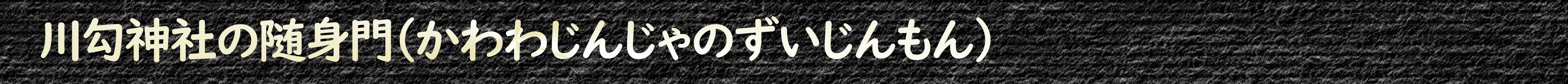
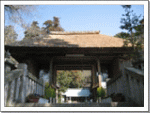
川勾神社の石段を上ると茅葺(かやぶき)屋根の随身(ずいじん)門があります。
二宮町内ではほとんど見られなくなった伝統的な屋根の葺き方ですので、大変貴重なものです。
門の中には木造随身倚像が安置されており、いにしえの風景が想像されます。
所在地/保管場所:二宮町山西2122 川勾神社


二宮町指定 史跡名勝天然記念物 昭和52年1月指定
室町時代からある古樹で、樹齢は推定450年から500年と考えられています。
カヤの木の材質は緻密で硬く、腐りにくいとされています。
実は食用になるだけでなく、油を搾って火種にもでき大変有用な木です。
今でも生き生きとした緑が芽吹き、若木も生長しています。
所在地/保管場所:二宮町川匂230 西光寺
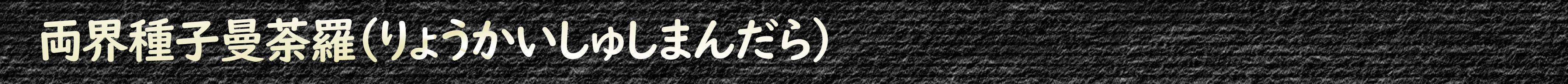
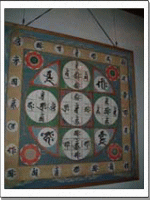
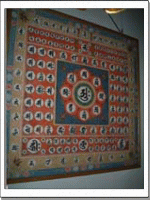
曼荼羅(まんだら)は二つあり、一つは寛政2年(1790年)の作であることが判明しています。
曼荼羅は真言密教の修行を終えた僧侶が、灌頂(かんじょう)の儀式に用いるものだそうです。
数多くの梵字が描かれ、美しい造形をともなっています。
所在地/保管場所:二宮町川匂230 西光寺
現在、公開しておりません。
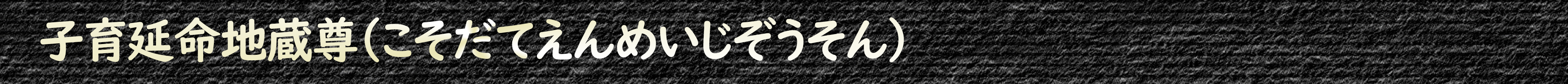
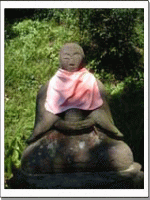
西光寺の山門を入った左手に「子育延命地蔵尊」があります。
子どもを守る仏様として信仰されています。
所在地/保管場所:二宮町川匂230 西光寺

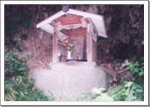
川勾神社入口の切り通しに祀られています。
かつてこの付近はでこぼこだらけの道で、子どもがよく転んでいました。
「袖が切れてもケガがなくて良かった」と、袖を切って供えたそうです。
所在地/保管場所:二宮町川匂230付近


古くから「川匂の湯」として広く知られ、豊富な鉱泉でした。
神経痛や皮膚病に効能があるとして、湯治に訪れる人が多く、明治37・8年頃の最盛期には、東京・横浜方面から来る人々で賑わっていたといいます。
大正12年の関東大震災で地下水脈が変わってしまったため、水量は僅かとなってしまいました。
所在地/保管場所:二宮町川匂2134-1

お稲荷さんの声を聞くことができる善波家のご先祖(およしさん)は、生前、何でも言い当てるということで東京からもたくさんの人が来ていました。
およしさんは昭和の始め頃に亡くなってしまいましたが、その後善波稲荷神社が建立され現在に至ります。
所在地/保管場所:二宮町川匂148付近 善波家



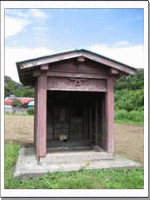
バンバ神、正式には祖母神といいます。
1月18日の祝日には幟(のぼり)を立ててお祭りします。
風邪の神・咳の神として、かつては風邪が流行るとお参りに来る人が少なくなかったようです。
所在地/保管場所:二宮町川匂226付近 二見家
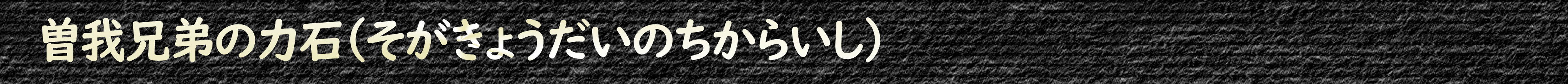
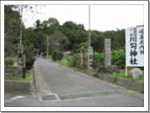
川勾神社前の二つの大きい石は「五郎、十郎の力石」といわれています。
曽我兄弟の五郎、十郎は重さ数百貫ある巨石の持ち上げ比べをし、兄の十郎は小さい方を、五郎は大きい方を軽々と両手で差し上げたといいます。
五郎の持ち上げた石にはワラジの跡が残っていますが、これは五郎が金剛力を出したときにくぼんだのであるといわれています。
所在地/保管場所:二宮町山西2122 川勾神社


お問い合わせ
二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班
住所: 〒259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
電話: 0463-72-6912
ファクス: 0463-72-6914
